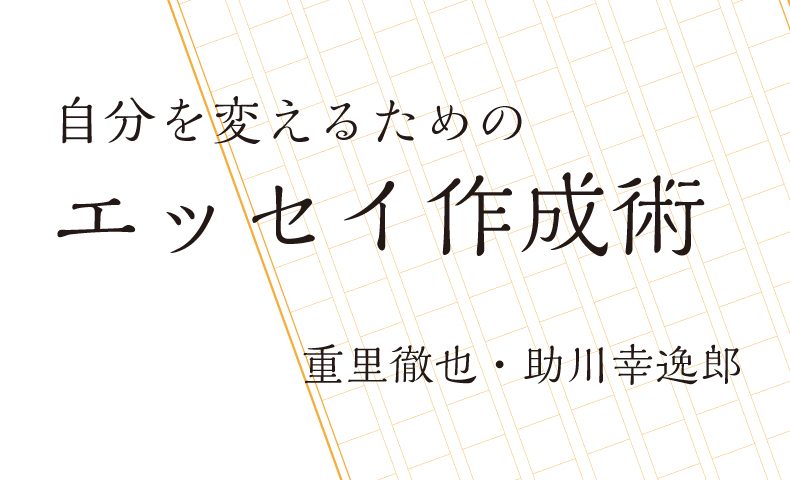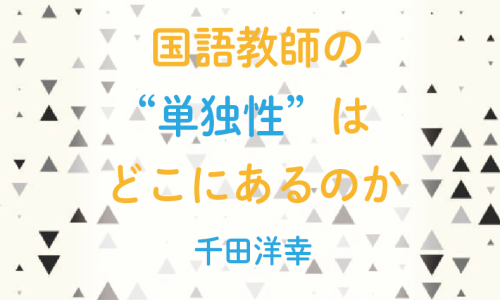「みんな」と「すごく」は「子どもの病」か?
私「ねぇ、仮面ライダーの変身ベルトぼくにも買ってよ。みんな持ってるんだ。」
母「みんなって、だれとだれよ。」
私「うーんと、シゲハルちゃんと、タカハシトンちゃんと。」
母「それって、あなたのお友だちで、持ってるのふたりだけってことじゃない。」
私「……」
幼い私はよく、こんな風にして母にやりこめられました。「みんな」が具体的に何を指しているか。そこを問いただされ、ことばにつまってしまう――多くのひとが、子ども時代に似たような経験をしていると思います。
それから、「みんな」と同様、「すごく」も私にとって「躓きの石」でした。
私「来月二日の日曜日に、巨人対ヤクルトの試合、観に行くから。」
父「その週はおまえ、水曜日から期末試験だろう? 日曜日に遊びにいくなんてとんでもない。」
私「でも、コンノ先生にすすめられたコンクールに出す作文、その試合を観たときのことを書く予定なんで、行かないとすごく困るのさ。」
父「困るって、どれぐらい困るんだ? 期末試験でビリになるより、作文コンクール出さないほうが困るんか? コンクールは、全員が出さなきゃならないわけじゃないんだろう?」
私「それは、そうだけど。」
父「春休みに京都に行った話でも書きゃいいじゃないか? 」
私「……」
「〈すごく〉をうかつに使ったゆえの失敗」――これも私にかぎらず、幼少期にしばしばやらかすシクジリといえます。
しかし。
「みんな」と「すごく」でまちがえるのは、果たして子どもだけでしょうか?
「大阪人ならみんな、芸人にいちばん必要なのは〇〇だと知っている」
「××大臣の答弁は、すごく不快に感じられた」
こういう言いまわしを安易にもちいて、信頼性を損ねるケースは、プロの書き手にもめずらしくありません。
「実感」の真実味を支えるのは「見える化」
子どもだった私も、うそをいうつもりで「みんな」や「すごく」をつかっていたわけではありません。
幼稚園児だったころ、仮面ライダーの変身ベルトを持ってないのは、クラスでじぶんだけのような気がしていた。
中学時代には、巨人対ヤクルトを観に行くことが期末試験より大事だと信じていた。
そういう「実感」が現状に即しているかどうか――「子どもの私」には、そこが見えていなかったのです。
「みんな」や「すごく」を繰り出せば、「実感」が事実かどうか検証をしなくても、話を先にすすめられます。このふたつは、ある意味「便利なことば」なのです。それだけに「プロ」の書き手でさえ、ついつい「みんな」や「すごく」に頼ってしまう。
逆にいうと、「みんな」や「すごく」をつかわないように心がければ、発言の説得力は増します。そういうことばを持ち出したくなったら、程度がどれぐらいなのかを具体的にのべるようにすればいい。
「そんな風であるのは、どれぐらいの数の(あるいは、どういう風な)人間か。」
「具体的にそれは、どこまで〈強烈〉なのか」
そこを「見える化」すれば、「実感」はおのずと現実に照合されます。
「見える化」の要は、「例」と「数値」
先日、「最近、印象にのこったニュース」というタイトルのエッセイを学生さんたちに書いてもらいました。次に掲げるのは、そのなかのひとつです。
最近、もっとも印象にのこったニュースは、将棋の羽生善治が、永世七冠の称号を獲得したことである。
私は将棋が好きで、中学の頃から、部活は将棋系に入っている。奨励会に在籍していて、プロに成り損ねた人と対戦したこともあるが、その人には、みんな勝てなかった。ものすごく強かった。
プロの棋士は全員、その人より強いわけである。そんな強者の揃う中で、一回でもタイトルを獲れれば大変なものだ。ところが羽生は、「永世」の資格が定められている七つのタイトル全部で、「永世」の称号を得た。
それぞれのタイトルによって規定に違いはあるが、五回から十回獲得しないと、「永世」の資格は与えられない。それを考えると、羽生のすごさがわかる。こんな天才棋士は、二度と現れないかもしれない。
これはこれで、まずい文章ではありません。羽生が強い棋士であることは、たしかに伝わってきます。けれども、羽生が「二度と現れない」レベルの天才であることは、このエッセイを読んだだけでは実感しづらい。
私は、これを書いた学生さんと話しあいました。
「奨励会にいたことのある人って、どれぐらい強かったの?」
「それはまあ、ものすごく。」
「みんな勝てなかったって、あなたは書いているけど、たとえばどんなヤツが負かされたわけ?」
「同じ高校の将棋部に、ぼくがぜったい勝てないヤツがいたんですよ。ぼくの勝てないそいつを、その奨励会にいた人、飛車角落ちで負かしちゃったんです。もちろんぼくも、飛車角落ちで対局して秒殺でした。」
「それを書いたほうが、奨励会にいた人がどれぐらいすごいか伝わるね。」
「そうですね。」
「あと、将棋のタイトル獲ったり、永世七冠になったりするのがどれぐらいたいへんか、具体的に数字とかでしめせない? それやったほうが、羽生さんの強さがはっきりすると思う。」
「それ、やってみます。」
翌週、学生さんは、エッセイの「改訂版」を携えて授業に現れました。
最近、もっとも印象にのこったニュースは、将棋の羽生善治が、永世七冠の称号を獲得したことである。
私は将棋が好きで、中学の頃から、部活は将棋系に入っている。奨励会に在籍していて、プロに成り損ねた人と対戦したこともあるが、その人はものすごく強かった。
その人がどれほど強かったか。高校の将棋部の仲間で、私が絶対に勝てなかったTを、その人は飛車角落ちで負かしてしまった。私もその人と飛車角落ちで対局したが、何度やっても秒殺された。
プロの棋士は全員、その人より強いわけである。そんな強者の揃う中で、一回でもタイトルを獲れれば大変なものといえる。タイトルは、今年から新たに叡王戦が設けられたが、これまでは七つ。将棋のプロ棋士は現在、一六二名いる。七冠を一つずつ分けあったとしても、タイトル保持者になれるのは二十人に一人もいない。
ところが羽生は、「永世」の資格が定められている七つのタイトル全部で、「永世」の称号を得た。
それぞれのタイトルによって規定に違いはあるが、五回から十回獲得しないと、「永世」の資格は与えられない。それを考えると、羽生のすごさがわかる。
羽生がはじめてタイトルを獲ってから、今に至るまでタイトル保持者はのべで二〇八名。そのうちの九九人が「羽生善治」なのだ。現役の棋士で、タイトル獲得回数で羽生に次ぐのは、谷川浩司の二十一回。それに続くのが渡辺明の十九回である。二位の谷川と三位の渡辺を足しても、羽生の獲得回数の半分にもならない。
こんな天才棋士は、二度と現れないかもしれない。
これなら、将棋に詳しくない読者も、羽生の天才ぶりが「二度と現れないレベル」であると納得できます。
私は学生さんに、
「奨励会にいた人の強さを物語る実例」
「プロ棋士がタイトルを獲る困難さと、そうした中で永世七冠を達成した羽生の偉大さを示す数値」
をつけくわえるようにアドヴァイスしました。
「実例」と「数値」。この二つをあげるようにすれば、てきめんに「見える化」が進み、文章の説得力は増します。
ただし。
「実例」も「数値」も、「読むひとに理解してもらうための手段」という意識を忘れないことが肝要です。
「こんなに実例が/数値が、正しさを証しているのだから、私の前にひざまずけ! 」
そういう姿勢が表に出すぎると、かえって読者の反発を買います。
文章は、「マウンティング」ではなく、「他人にわかってもらうこと」を目ざして書く。それが「文章作成術」の原点であることを、忘れないようにしたいものです。