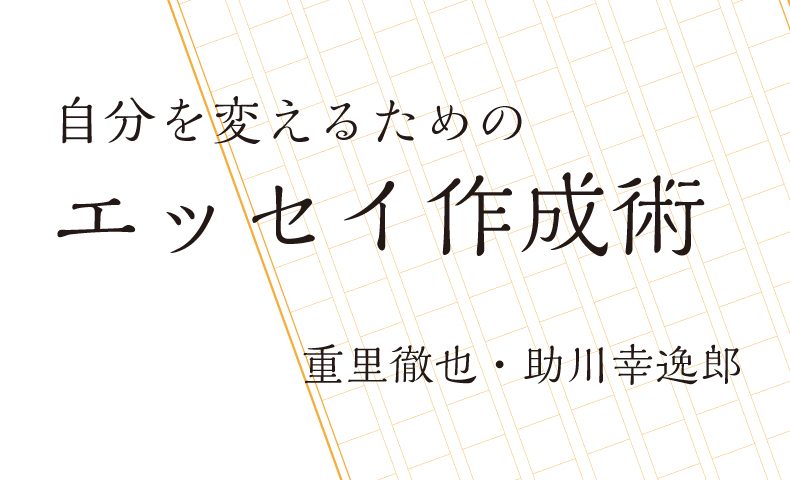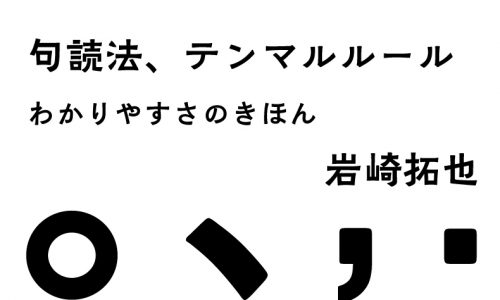私にとって、エッセイを書くうえで最もつらいのは、書き始める時です。自分の頭や心にはモヤモヤとしたものがある。それに何とか、言葉という形を与えたい。でも、なかなかうまくいかない。
どうすればいいか悩んでしまいます。これを「白紙の恐怖」と呼ぶ人もいます。
そんな時に有効なのは、自分にとって手持ちのカードを切って、書き始めることです。自分に身近で、そのことなら、ある程度、わかっているよということを冒頭に持ってきて、文章を始動させるのです。
私がすぐに思いつくカードは、2つあります。これで何とかなることが多いのです。
1つは自分が日頃、考えていること、こういうことはあまり、いわれることがないけれど、けっこう面白いかもしれないということを披露するのです。それは、長年、思ってきたことの場合もあるし、あるいは、最近のニュースに接して、思いついたこともあります。随分と前に人から聴いて温めてきた言葉もあれば、愛読している作家の片言一句もあります。
たとえば最近、私が書いたある書評の書き出しはこんな具合でした。
教養の大切さを説く声をよく聞くが、それでは一体、教養とは何なのか。一つの答えをとりあえずいえば、歴史を知ることではないか。
おそらく突拍子もない考え方ではないだろう。司馬遼太郎が相変わらず人気が高いのも、歴史を知ったり、楽しんだりすることで、広義の教養が身についていく感覚があるのも理由の一つのはずだ。
「教養とは歴史を知ることではないか」というのは、学生時代に友人が語ってくれた言葉です。つまり、約40年前に聴いた文言ということになります。
以来40年間、私はさえない人生を送りながら、この言葉を抱き続けてきました。そして、さえない人生の重さで、これは真実ではないかな、と思っています。歴史についての本を書評するにあたり、私においてはとっておきの言葉を使ったわけです。
もう1つ。「司馬遼太郎」は私には数少ない切り札の1枚です。30代のころ、猛烈に司馬を読みました。新聞連載の執筆で、司馬の小説の舞台もいくつか訪ねました。司馬が取材した地元の歴史家の方々にも何人か取材しました。
若いころに司馬と親しかった黒岩重吾にも、司馬の話を聴きました。吉村昭や古川薫など、司馬に批判的な作家の言葉も随分とうかがいました。他にもさまざまな作家や評論家に司馬についての評を聴いた蓄積があります。
それだけではありません。私にとって、司馬は同郷で、大学の先輩なのです。司馬の言葉遣いも、司馬の過ごした街の空気も肌でわかるという思い込み(たぶん、思い込みでしょう)があります。
だから、人と話していて司馬の話題になると、「しめた」と思うのです。司馬について書く時には、もし、批判されれば、「おうおう上等じゃないか。おまえより、おれの方が司馬のことを知っているよ」と逆にかみつくぐらいのハッタリを胸に抱いています。幸いに、まだ批判されたことはなく、馬脚を表さずに済んでいるのですが。
エッセイを書く時には、ハッタリでいいから、「私にとっての司馬」のようなものを持っているといいです。話題をそこに持っていけば、何とかなるという切り札です。
切り札はたくさんあった方がいいと思います。私は30代のころから、意識して切り札を増やそうと思っているのですが、なかなか増えません。
たとえば、「親鸞」を切り札にしたかったのですが、全く勉強不足です。「源氏物語」については、友人たちと勉強会をしていますが、ストーリーや登場人物の相関もあやふやです。「吉本隆明」や「大阪論」も考えるのですが、私より詳しい人はゴマンといます。
話が横道にそれ過ぎました。とにかく、日頃、考えていることや思っていること、自分が得意だと勝手に思っていることから、エッセイを書き始めるという方法が1つ目の書き出し方なのです。
エッセイの書き出し方の2つ目は、シーンを描くという方法です。ある場面を映画かテレビドラマのように思い浮かべて、描き出すのです。
新聞のコラムで(コラムは正確に言うとエッセイとは違いますが)、けっこう多いのが、会話で始めるものです。「 」で始めると文章が意外に書きやすいのです。会話も、場面をその場に現出させる典型的な方法といえるでしょう。
たとえば、こんな感じです。
「それ、犯罪だよ。わかっているの」
女性のきっぱりとした声の後、しばらく朝の満員電車は沈黙が支配した。不思議な緊迫感を感じて、私は眠気が吹き飛んだ。一体、何があったのだろう。
次の駅で茶色のコートを着た中年の男が降りて、そそくさと走っていった。どうも、女性が痴漢の被害に遭い、当然のことだが、それを厳しくとがめたらしい。
読者が思い浮かぶような何げない場面(この場合は「朝の満員電車」)とあまり日常的ではない事件(この場合は「痴漢」)を組み合わせた書き出しです。
これは、私が何年も前に通勤途中で遭遇したシーンです。「犯罪」という言葉が鋭くて、記憶に残っています。まだ、使っていません。どんなテーマについてのエッセイに使えるか、わかりません。ただ、さまざまな場面を記憶の中に持ち札として持っておくといいように思います。
常日頃に考えていることから書き出すか、あるシーンから書き始めるか。他にもあるかもしれませんが、この2つを覚えておくと、エッセイは書き出しやすいはずです。
この2つの例を私が愛読する作家の作品から紹介しましょう。まず、前者の例。
どこの国の都にも忘れられない匂いというものがある。私がおぼえているのはパリなら冬の夜の焼栗屋の火の匂いである。初夏の北京はたそがれどきの合歓木の匂いでおぼえている。ワルシャワはすれちがった男のウォトカの匂いでおぼえている。ジャカルタの道には椰子油の匂いがしみこんでいた。
開高健『ベトナム戦記』(朝日文庫)の冒頭です。「匂い」に特化して、海外のいくつかの首都の記憶を描いています。世界中の首都の匂いを知っている作家だからこそ書ける「つかみ」です。
この文章を書くために費やした作家の日々が思いやられます。文章を書くのは元手がかかるものです。そして、読者は果たして、サイゴン(現在のホーチミン市)の匂いはどういうものなのか、と期待が高まります。
開高健は視覚だけでなく、聴覚や触覚を大事にした作家です。そこにも、この作家の現代的意味があるでしょう。嗅覚も重視した小説家で、この文章は匂いによって、読者を誘う卓越した書き出しだと思うのです。
次はシーンを書く例です。
ロジャ・メイチン君は、まだ二十代の日本語学者である。洛北一乗寺の小さなアパートに住んでいて、二、三の大学の講師をつとめている。かれの居住地のあたりを、
「深泥池(みぞろがいけ)ゆき」
というバスが通るらしい。その深泥池という語源について数日考えこんだあげく、浪華東郊の拙宅にやってきた。
「深泥池という池をご存じですか」
と、美しい敬語で問いかけてきた。
司馬遼太郎『街道をゆく』第1巻の「竹内街道」の章の冒頭です。そうです。困った時の司馬遼太郎です。また、「切り札」を切ってしまいました。
この場合、「深泥池」という固有名詞が深く印象に残りますね。強い響きです。そして、それを外国人が話している。西洋人が「ミゾロガイケ」と歯切れよく丁寧に話す場面が目に浮かんできます。
そして、これからどう転んでいくのだろうと、これも先を読みたくなる書き出しです。
自分にとって身近な題材、考え続けてきた手持ちのカードを切るか、あるシーンをその場に現出させるか。いずれも、上陸する(エッセイを書く)ために、橋頭堡(きょうとうほ)を築くようなイメージです。
どちらの方法でもかまいません。とにかく書き始めましょう。徐々にエンジンが温まり、スピードも上がってくるはずです。