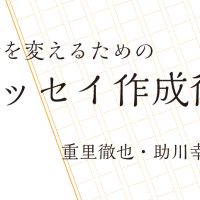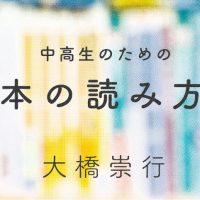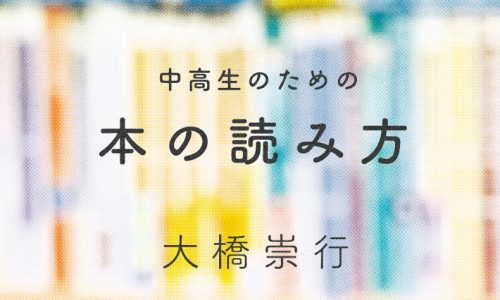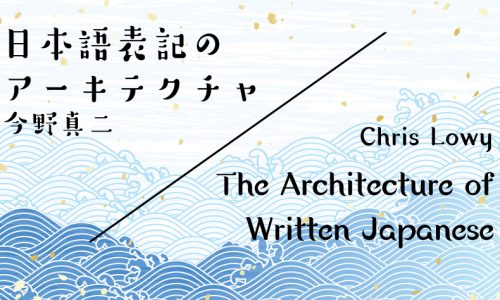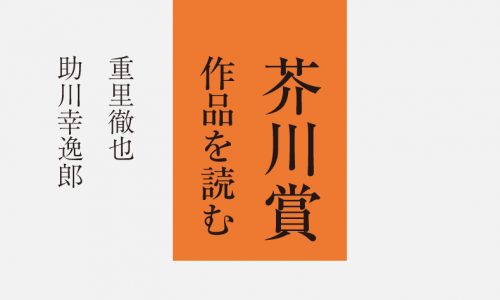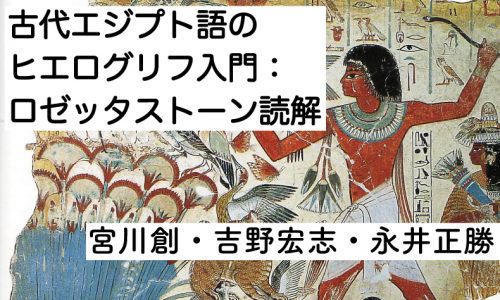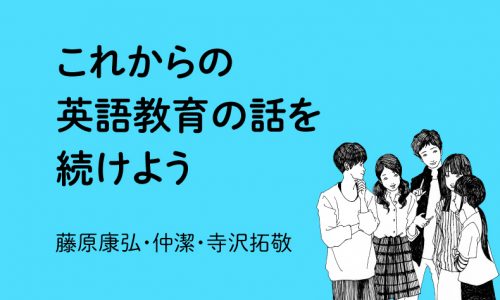教科書は「読書」に含まれますか?
ここで少し視点を変えてみましょう。
高校生でも、間違いなく毎日のように読んでいるものがあります。そう、学校の授業で使っている教科書です。
私は大学で 中学校・高校の国語の教員免許取得を目指している学生の指導を担当しているので、ほとんどの教科書会社が刊行している中学校と高校の国語の教科書に目を通しているのですが、今の教科書はとてもよくできているものが多くなっています。
国語に関していえば、たとえば中学校の教科書に、文章を読んで、書いて、他の人の話を聞いて、自分の考えていることを大勢の人の前で話すという、言葉を使った活動の基本的なことは、教科書1冊をしっかりと読んでいけばほとんど身につけることができるように作られています。
また、たとえば高校の日本史の教科書は、とてもよくまとまっています。隅から隅まで何度も読み返していけば、他に参考書や問題集を買わなくても大学入試で合格するくらいの知識は身につきます。
大学入試までの勉強というのは、各教科につき「本1冊」を「読書」すれば良い。
こう考えると、とても簡単なものに思えませんか?
教科書とは、基本的な知識を身につけるためにはいちばん効率の良い形で非常によくまとまった「本」であり、教科書を読むことは立派な「読書」になるはずなのです。
けれども、教科書を読むことを「読書」だと感じる人は少ないでしょう。どうしても教科書を読むことは「勉強」というくくりになってしまいます。
これはおそらく、最初に書いた私が本を「読んでいない」という感覚と、似たようなものではないでしょうか。本を読むことが義務感と結び付いてしまうと、なかなか「読書」として認識することができないのです。
逆に、自分から興味を持って読んだものであれば、どんなにむずかしい本でも、「読書」をしたような気持ちになることができます。
数年前、たまには親孝行をしてみようと、母をオーストリアのウィーンに連れて行ったことがあります。
私は高校生のときに世界史をサボっていたし、美術についてほとんど勉強せずに行ったので、ハプスブルグ家や「世紀末ウィーン」と呼ばれる19世紀末にウィーンで起こった芸術運動についてほとんど知らない状態で街をめぐっていました。それに対して母は、絵を描くことを趣味にしていて、二科展という1年に1度行われている展覧会で何年も続けて入選している人なので、ウィーンの街と芸術についてはとても詳しい。だから、ほとんど母の案内で、街の美術館や王宮を回っていました。
それで、帰国してから母が案内してくれた場所のことが気になって、遅ればせながらウィーンについての本を読むようになりました。歴史や美術についての専門書もかなり読んだのですが、これがとてもおもしろい。専門書を読むという、いつも大学の授業をするためにしているのと同じことをしているのに、おもしろさがまるで違うのです。
そしておそらく、このときに私がしていたのが「読書」だったのだろうと思います。
つまり「読書」とは、自分が興味を持ったものについて書かれた「本」を読むことなのではないか。私はこのときにふと、そんなことを考えたのです。