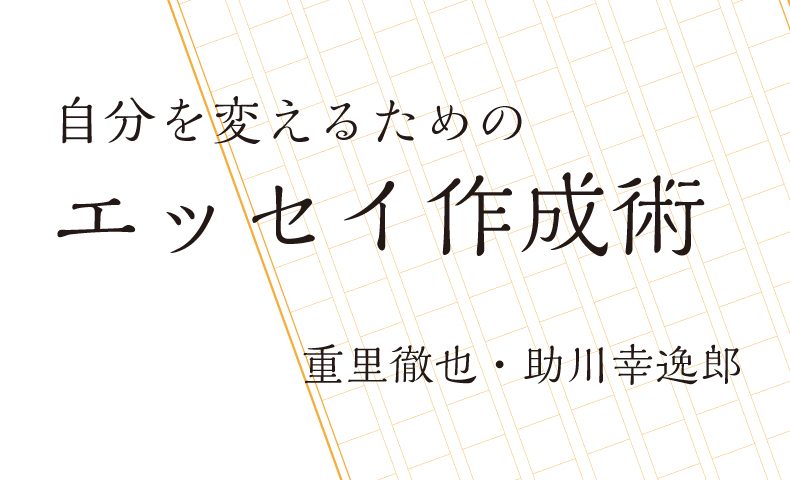▪ なぜタイトルが大切なのか
私が大学生だったころ、ある先生がこんなことをいっていました。
「学生が書いたレポートは、タイトルを見るだけでだいたい出来映えの予測がつく。だから、よほど注意してレポートの題名はつけなくてはならない。」
じぶんが学生さんのレポートを採点する立場になって、この言葉の意味が身にしみてわかりました。
たとえば、夏目漱石の『こころ』をテーマにレポートを出してもらうことにしたとします。このとき、「『こころ』について」というタイトルで書きはじめたらどうなるか。「『こころ』にかんする雑多な情報」や「漠然とした読後感」を、未整理なまま並べたてたものになる危険性が大です。
これに対し、
「先生はなぜKをじぶんの下宿に引き入れたか」
という題目を掲げたとすると――この場合、「『なぜ』に対する答えを書く」という「縛り」が発生します。「答え」の根拠をあげることも必要になってくる。結果として、「何をどう書くか」について、自然にピントが絞れてくるわけです。
対象のどの部分に光を当て、いかなる角度からそこにアプローチするか――その点を、書き手当人と読者の双方に対し明確にする。適切なタイトルをあたえることの最大の効用はそこにあります。
▪ タイトルのつけ方は4通りある
こんなことを記すと、
「文章を書くとき、題目が大事なのは私にもわかる。問題は、具体的にどうすればよいネーミングをできるかだ。そこがじぶんにはまったく見当がつかない」
お読みいただいている方から、そういうお叱りの声が聞こえて来そうです。
私は、エッセイや小説のタイトルのつけ方を、4通りのパターンにわけて考えています。この分類は、あくまで「とりあえずのもの」。他のわけ方もあることを否定するつもりはありません。ただ、「仮のパターンわけ」であっても、それを頭に入れておくと、じぶんの文章に名前をあたえる作業が格段に容易になる。どこから手をつけていいかわからなかった「ネーミングという営み」に、具体的な「とっかかり」ができるからです。
以下に、私の考える「タイトルのつけ方の4つのパターン」をあげてみます。
① 主要人物の名称にちなむ
(著名作品の例)トルストイ『アンナ・カレーニナ』・川端康成『伊豆の踊子』
② 「叙述の対象となる出来事」の舞台を使用
(著名作品の例)志賀直哉『城の崎にて』・三島由紀夫『金閣寺』
③ キーワードやキーアイテムをかかげる
(著名作品の例)芥川龍之介『鼻』・村上春樹『ノルウェイの森』
④ 「叙述の対象となる出来事」や「主題」を象徴的にあらわすフレーズをもちいる
(著名作品の例)島崎藤村『破戒』・太宰治『人間失格』
これらのパターンに、すんなり収まらない作品も少なからず存在します。そういう「例外」も、ていねいに見ていけば、たいていは右の4つのパターンのどれかをひねったものとわかる。
『吾輩は猫である』というタイトルからは、語り手が猫であることが伝わって来ます。これは、①の変形版と見てさしつかえないでしょう。
谷崎潤一郎の『細雪』は、蒔岡家の四姉妹の生活を描いた長編。谷崎は『三姉妹』という題名も考えていたようです(英訳版のタイトルは、The Makioka Sistersになっています)。
『細雪』の「雪」は、四姉妹の三番目にあたる「雪子」からとったと、谷崎みずからが書いている。さらに、日本の古典の世界では、「雪」は「散る桜」にしばしば見立てられ、「はかなさ」や「無常」を象徴します。
『細雪』というタイトルは、一見しただけでは意味がわかりません。そこにはしかし、「姉妹のなかでもとくに雪子が重要人物であること」が暗示されている。同時に、「関西上流家庭の、戦争で失われた優雅な暮らしを描く」という「主題」も託されています。実は、①と④を兼ねた、たいへん高度なネーミングというわけです。
(次回につづく)