2025年3月刊行
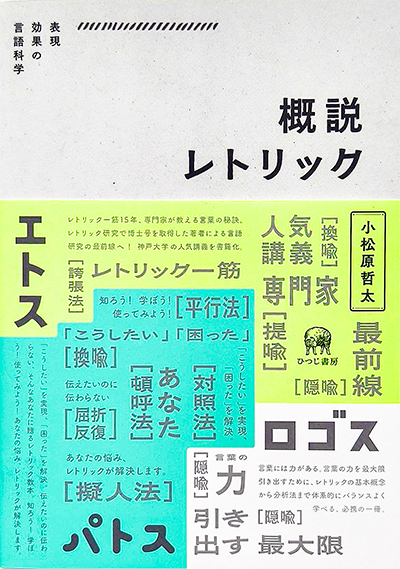
概説レトリック
表現効果の言語科学
小松原哲太著
A5判並製カバー装 定価2500円+税
ISBN978-4-8234-1297-4
装丁:村上真里奈
Introduction to Rhetoric: A Linguistic Perspective
Komatsubara Tetsuta
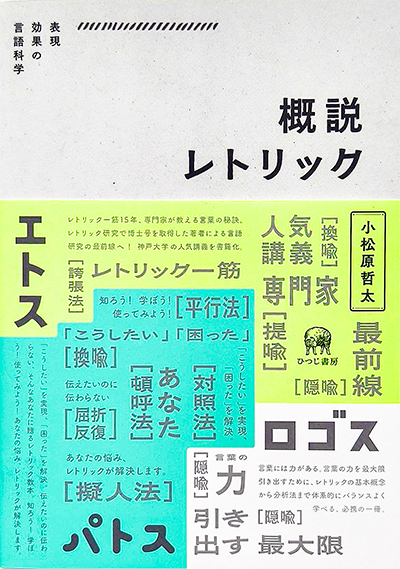 |
概説レトリック表現効果の言語科学小松原哲太著 A5判並製カバー装 定価2500円+税 ISBN978-4-8234-1297-4 装丁:村上真里奈 Introduction to Rhetoric: A Linguistic Perspective |


